現状維持企業と成長企業が取り組んでいることの違い

本コラムでは、株式会社デフチューンの大原が、10人から20人規模の地方中小企業が現状を打破し、これからのビジネスを展開するために必要な要素について、顧客事例を参考に考察したものです。成功している企業の特徴として「積極的な情報発信」と「組織のマルチスキル化」を挙げ、最初に取り組むべき施策として、自社の強みを資産化する「情報発信」を推奨しています。
・案件打ち切り後から動いていては遅い
・資産作りとして「情報発信」の重要性
目次
01. 現状維持に陥る中小企業の課題
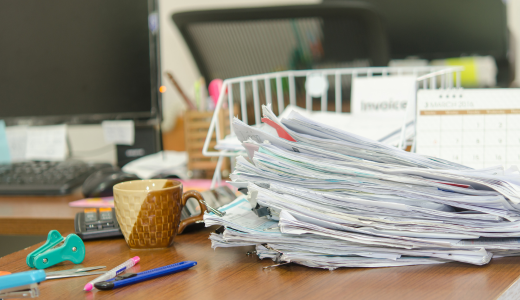
1-1. 現状維持では意味が無い
「事業を拡大させること。会社を成長させることについて、向き合えていない」・・・そんな悩みを抱えている中小企業経営者の方、実はいらっしゃるのではないでしょうか。特に赤字は出していないし、既存のお客様に対して迷惑もかけていない。安定的に事業活動はできている。しかし、経緯はそれぞれ形があるにせよ、最初に経営者としてビジネスをすると決めた時、大きな夢や目標はありませんでしたか?私はそういう話をお聞きするのが大好きです。
1-2. 課題に目を背けるのは命取り
私が、最も尊敬している経営者の一人の方から、「経営者たるもの会社を成長させ続け、拡大させることが使命である、その努力を辞めたら経営者として失格」という話を聞いたことがありました。私はそれを聞いたときに、純粋にかっこよさを感じ、ブッ刺さりました。
02. とある製造業社長とご縁がありご挨拶に伺った時

2-1. 既存案件が続くとは限らない。先々の戦略は?
先日、交流会の出会いをきっかけに、ある金属部品加工メーカーさんの工場を訪問させていただきました。フランクにご挨拶と事業紹介をしまして、話が進む中で、非常に利益率が低い案件があるというお話をお伺いしました。
- 単価がやすい
- たくさんの数量を生産して利益が出る
- 毎月決まった数量のオーダーはある(全体発注数の1割ほどをカバー:補給品)
- 工場の立地的観点から夜間運営ができない
結論としては、この案件について社長ご本人としては、撤退したいと考えていました。そもそも発注先の調達部も今後一つの工場に集約することを計画しているため、いずれはオーダーがなくなる可能性もあるという状況でした。
2-2. 時に既に遅しになれば本当に厳しい
会社としては、後者の方が圧倒的に危険ですよね。この案件の代わりを探すために交流会に参加されているようでした。現状は、それに代わる新規案件や事業の話はなく、撤退に踏み切れない状況で、むしろ生産場所を変更されて、打ち切りになるのが早いかもしれないわけです。
03. 都合よく案件が降って来ることはないし、本質的な解決ではない。

3-1. 目的なき交流会は非効率
新規案件獲得のために交流会へ参加し、もし仮に依頼があったとしてもそれで安心できる状態では到底ないはずです。毎週・毎月のように交流会に参加し、受注できるような商売ではないことは社長が一番分かっているかと思います。
3-2. 最大の魅力は伝わっている?
交流会 → 日程調整 → 移動 → 打ち合わせ、と、かかってくるコストに対し、投資回収の見込みは不明。なかなかこの流れでは会社の魅力が伝わりきらず、他者との差も伝えにくいですよね。
04. 成功している中小企業が実践する2つの戦略

おそらく、地方には、同様の中小企業がたくさんいらっしゃるかと思います。弊社のお客様や毎年成長をしている中小企業を見て、違いを考えてみました。では、新しい顧客を獲得し、成長している中小企業は何をしているのでしょうか?私が成功事例を見てきて感じるのは、以下の2点です。
4-1. 積極的な情報発信
自社の思い、ブランド、能力、スキルをバランス良く外部へ向けて発信し、世間に知られることで認知度を高めている。専門的な部分は外注を活用しプロのチームを入れつつ、企画力といった社内で身につけるべきコアな部分は内製化して進めている。そうすることで安定的に情報発信できる環境を整えて、自社を認知させていくことで営業活動・採用活動に繋げています。ここに対する投資を経営者が腹を括って進めているところが、最も違うように感じます。
4-2. 組織体制の強化(マルチスキル化)
昨今の人手不足の観点からも非常に有効な戦略であり、特定の機械を一人しか使えないといった業務の「属人化」を避けて、組織として案件に取り組む体制を構築しています。一人の従業員が複数の業務スキルを持つ「マルチスキル化」を推進することで、担当者不在時の生産停止という致命的なリスクを回避しています。この戦略によって、採用が難しい状況でも、限られたリソースで柔軟に対応できる強い組織を作っています。
05. 最初に取り組むべき施策としての「情報発信」

5-1. 経営者が意思決定をしてスタートです
自社の情報を外部に「発信」することを是非検討してみてください。社内では当たり前になっている作業、スキル、人などが、実は社外にとっては魅力的なコンテンツやエンタメ的な要素である可能性が十分にあります。発信したコンテンツは、すぐに結果が出なくとも、半永久的に残る資産となり、動画や写真、SNSプラットフォームなどを活用していくことで中長期的に結果を見込めます。
5-2. 新規事業も仲間集めも情報発信がめっちゃ大事
弊社では、お客様がどのようなコンテンツを発信すべきか、どのような戦略が最適かといった部分から、丁寧にサポートいたします。「情報発信を始めたいけれど、何から手をつければ良いか分からない」とお悩みでしたら、ぜひ一度、お話をお聞かせください。